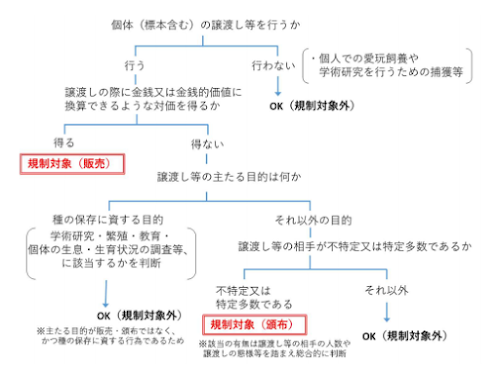今年はゲンゴロウ頑張るぞー、と気合が入っていたのですが、気合が入り過ぎたせいかゲンゴロウが凄いことになっています。
既に40匹以上の幼虫が採れており、上陸して土に潜ったものだけで8匹。
そのうち1匹が今日成虫になりました。
私は延べ数年間ゲンゴロウ繁殖経験がありますが、生まれたばかりの白いゲンゴロウを見るのは初めてです。
朝起きたら既にこの状態でしたので脱皮シーンが見られなかったのは残念です。
このゲンゴロウ、6月18日くらいに強制上陸させたのですがなかなか土に潜らずさんざんグズったあげく6月23日にやっと潜りました。
長さは約8cmくらいだったでしょうか。
余りにもグズるので何回も上陸させたり水に戻したりするのが面倒になり、下のように水が入った容器を土入りのプラケに入れて勝手に上陸するのを待つことにしました。
写真は既に容器から水を抜いてある状態で撮りましたが、上陸までは満水状態で水草を多めに入れておき幼虫が自力で這い出ることができるようにしてありました。
この第一号の幼虫君は飼い主孝行なことに容器の真下に蛹室を作ってくれたので、まさにシースルーな感じで観察できとても楽しませてくれました。
容器をスポッと抜けば間近に観察できます。
下は蛹になって数日した頃(7月2日)です。
そして、下が羽化直前(7月12日)
カブトムシと同じようにもっと茶色くなるのかと思っていたのですが、実際のところ目と手足を除けば意外と白いままなんですね。
今朝(7月13日)に起きたらもう脱皮して成虫になっていました。
蛹の時期に段々丸っこい形になっていくのだと思っていましたが違うんですね。
蛹は最後までスリムなままで脱皮と同時に横幅が出ることが分かりました。
そのあたりも蛹になるとほぼ成虫と同じ形になるカブトムシと違いがありますね。
そして夕方。
だいぶ羽に色がついてきました。まだ薄いあめ色です。
ここまで苦労して育ててきたので感無量です。
でも、今年は休む間もなくなりそうです。
なんせ、3齢幼虫や3齢間近の2齢幼虫たちが入った穴あきのペットボトルが上段の金魚水槽を完全占拠しています。
金魚の稚魚達が同じ水槽内に同居しているのですが、ペットボトルで仕切られているので食べられる心配はありません。
スペースが限られたベランダでの飼育ですので生き物同士の相性を考慮しつつ同居させる必要があるんです。
1齢幼虫や脱皮したての2齢幼虫が入ったポリコップもベランダの排水溝にズラリと並んでいます。 ゲンゴロウ千本ノックとはまさにこのこと。
正直これだけいると餌代がかなりかかりますし朝晩2回の給餌もしんどいのですが、今年はやるぞ、と決めたからには最後までやり遂げたいと思います。
これだけの数を経験するとお世話の作業もこなれてきますし、少しでも楽に安くやる方法を考えて工夫しますので、うちのベランダはさながらゲンゴロウ工場のごとくなってきました。
まだまだ一令幼虫が日に3匹も出てくる状況ですのでもしかしたら100匹までも届くかもしれません。。
引き続き頑張るぞー。