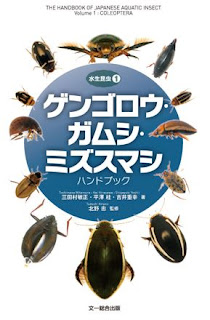先々週、今度こそホンゲンをゲットすべく、再び新幹線に乗って田舎の方に行ってきました。ホテル代、レンタカー代など含めると結構な出費ですが、フィールドワーク2回目の正直でホンゲンをゲットすることが出来ました。
ホンゲンがいたのはこんな小さな池、というか水たまりです。
こんなところは地図にも出ないので車で走って探すしかないんです。
この場所が見つけられたのは結構幸運だったと思います。
カンガレイやヒルムシロ、ホソバミズヒキモ?らしき水草が生い茂っていました。
ミズオオバコやオモダカも生えており、絵にかいたような自然豊かな水たまりです。
水たまりに近づくと同時に向こう岸付近で泳ぐゲンゴロウの姿が見え、それまでの苦労と比べてあまりにも呆気ない登場に驚きました。
タモ網でガサガサすること2時間。5匹ものホンゲンゴロウと1匹のクロゲンゴロウを捕まえることが出来ました。
この水たまりにはまだ結構な数のゲンゴロウがいて、遠くて網が届かなかったり、取り逃がしたりしたものも含めれば10匹以上を目撃したと思います。
動画も撮ってきました。
必ず3倍に殖やして戻すからね、と誓ってオスメス2ペアをお持ち帰り、オス1匹をリリースしました。
ちなみに、一緒に入っているコオイムシやガムシは別の池で捕まえたものです。
コオイムシは調べたところによると、巻貝を食べるとのことだったのでお持ち帰りし、ガムシは大量に水草を喰らう悪者ですので、帰りがけに元居た付近の川に放しました。
ホンゲンはその昔、少年時代に田舎で電灯に飛来したものを捕まえたことはあったのですが、水中を泳いでいるものを網ですくったのは初めての経験です。
とても楽しいひと時でした。
この水たまりの付近は本当に自然が豊かで、色々な種類のトンボがいるのも魅力的でした。
じゃじゃーん、こちらは生まれて初めてとらえたギンヤンマ。
うちの6歳児はカマキリ先生で観て以来、この美しいトンボのとりこになってしまい、思い出しては「パパー、ギンヤンマ捕まえたことあるー?」としつこく聞いてくるのです。
そんな簡単じゃねーよ、と思いつつ「いやー、無いんだよね」としか言えてこなかったのですが、ついに面目躍如の時が訪れました。
6歳児大喜び。弾丸のような速さで飛んで来たこいつをタモ網で完璧にミートした姿がよっぽどかっこよく見えたのか、その後のリスペクト感が半端なかったです。
下の写真は、やはり初めてとらえたという以前に、初めて存在を知ったヤブヤンマ。
オオルリボシヤンマかも?正直、見分けがつきません。
オニヤンマとギンヤンマ以外にこんなデカいトンボがいるなんてことは初めて知りました。
捕まえた個体はまだ色が黄色っぽいので未成熟な個体ですが、この水たまりは別の美しいスカイブルーの成熟個体が縄張りにしており、他のトンボをデカさ速さ力強さで圧倒し、水面からはじき出しているのでした。
結構ねばったのですが、弾丸を上回るような速さで飛び、こちらをあざ笑うかのようにホバリングするそいつだけは、どうしてもとらえることができませんでした。
ちなみにオニヤンマも捕まえました。比べると違いが分かると思います。
さて、持ち帰ったゲンゴロウ、来シーズンには大量に産卵させて育て、またこの場所に戻しに来たいです。